脚立のような道具は、見た目が似ている椅子や三脚などとも混同されやすく、「本」や「個」で数えてしまう人も少なくありません。
本記事では、脚立を正しく数える単位や、その背景にある考え方を徹底解説します。また、踏み台やはしごといった似たアイテムとの違いにも触れ、数え方を比較しながらわかりやすく整理しました。
さらに、プロの現場でもよく登場する「尺」表記の意味や、数え方との混同が起きやすいポイントにも触れていきます。
脚立の正しい数え方とは?「1脚・2脚」で合ってる?

脚立・椅子・三脚との共通点と違い
脚立は基本的に「1脚(いっきゃく)」「2脚」と数えるのが正解です。
脚立、椅子、三脚には共通して「脚が複数ある」「自立する」「使用者が登ったり支えたりする」という性質があります。
このため、それぞれ「○脚」という助数詞が自然に用いられているのです。
脚付き道具の助数詞比較
| 道具の種類 | 主な使用場所 | 自立するか | 正しい数え方 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 脚立 | 建築・家庭作業 | ○ | ○脚 | 作業用で自立可能な構造 |
| 椅子 | 家庭・オフィス | ○ | ○脚 | 座るための家具、自立型 |
| 三脚 | 撮影・計測機材 | ○ | ○脚 | 機材を安定させるための支柱 |
このように、脚立は「椅子」「三脚」と同じく“自立する脚付きの道具”であるため、「脚」という助数詞が用いられます。
ただし、それぞれの道具は使用シーンや目的が異なり、椅子や三脚は日常用品や撮影機材として扱われるのに対し、脚立は建築現場や家庭の作業用具として扱われるという違いがあります。
なぜ「個」「本」ではなく「脚」で数えるのか?
「個」や「本」も道具の数え方として使われることがありますが、それらはあくまで汎用的な単位です。
一方で、「脚」はより具体的で形状・機能に合った助数詞となるため、脚立のように脚付きかつ自立型のものには最適とされています。
また、「本」は棒状のものに使うのが一般的で、脚立の構造には適していません。
「脚立」「踏み台」「はしご」の数え方の違い

踏み台やステップ台はどう数える?
踏み台やステップ台は、脚立よりもコンパクトで、主に室内でのちょっとした昇降に使われる道具です。
一般的には脚付きで自立する構造を持っているため、「○脚」という数え方が使われます。
ただし、全ての踏み台が「脚」で数えられるわけではありません。
たとえば、金属製のステップ台や家庭用のスツールのように、構造が脚付きで安定性が高いものは「○脚」でカウントされるのが自然です。
一方で、プラスチック製の一体型構造の簡易踏み台や折りたたみ式で脚のように見えない形状のものは、「○個」と表現されることも多くあります。
このように、踏み台の数え方はその形状・構造・使用シーンにより柔軟に変わることがあるため、場面に応じた使い分けが重要です。
特に通販サイトの商品説明や購入時の問い合わせでは、「個」「脚」どちらの表記も見られるため、文脈で判断する必要があります。
はしごとの数え方は同じ?違う?
はしご(梯子)は「1本」「2本」と数えるのが一般的です。
これは、はしごが棒状の構造を持っており、垂直に立てかけて使用する道具だからです。
「本」という助数詞は、もともと細長いものや棒状のものを数える際に使われるもので、たとえばペンや木材、釣り竿などと同じ分類になります。
脚立とは異なり、はしごは自立しません。使用時には必ず壁や柱などに立てかける必要があり、自立構造を持たないため「脚」で数えることは不自然とされます。
また、脚立が使用者の体を支える目的で設計されているのに対し、はしごは上に登るための通路としての機能が強く、構造的な役割にも違いがあります。
このように、助数詞は物理的な特徴と使用目的に密接に関係しており、単なる見た目の類似ではなく、構造の違いによって自然と数え方が分かれるのです。
脚立のサイズやタイプで数え方は変わる?

二段・三段・伸縮式脚立の数え方
二段脚立や三段脚立、さらには伸縮式の脚立も、すべて「○脚」で数えます。
段数の違いはあくまで製品の仕様であり、数え方の単位には影響を与えません。
段数はあくまで脚立の高さや使い勝手の違いを示す指標であり、脚数や構造自体には変化がないため、数える際の助数詞は一貫して「脚」となります。
また、伸縮式の脚立については、可動部分があるため一見して特殊な構造にも見えますが、基本的には「脚」の形状を保ったまま長さが調節されるものであり、通常の脚立と同じ分類になります。
むしろ、段数や伸縮性などの違いを表す際には「段」や「タイプ」、「モデル」などの別表現が用いられます。
プロ用脚立(尺表記)との違いに注意
建設現場などで使われるプロ向けの脚立には、「3尺脚立」「6尺脚立」などの表記が見られます。
この「尺」は長さの単位であり、数え方とは別です。
つまり、「6尺脚立1脚」といった表現が正確な言い方になります。
「尺」という表現は、脚立の高さを示すのに便利な伝統的単位として業界内で広く使われており、現場では「6尺の脚立を2脚持ってきて」といった具体的な指示に役立ちます。
数え方と寸法がセットで表現されるケースが多いため、混同しないよう注意が必要です。
サイズや形状に関わらず「脚」でOK?
小型の室内用脚立から、大型の工事用脚立まで、基本的にはすべて「脚」で数えます。
脚立の形状や大きさは単位を左右せず、構造的に脚があり自立するものなら「○脚」で統一されます。
折りたたみ式、片側開閉型、脚が四方に広がる構造など、さまざまなデザインが存在しますが、それらすべてに共通するのは「脚で立つ」点です。
このため、脚立というカテゴリに入るものであれば、外観に差があっても助数詞は変わりません。
「脚立の尺」に関するよくある疑問
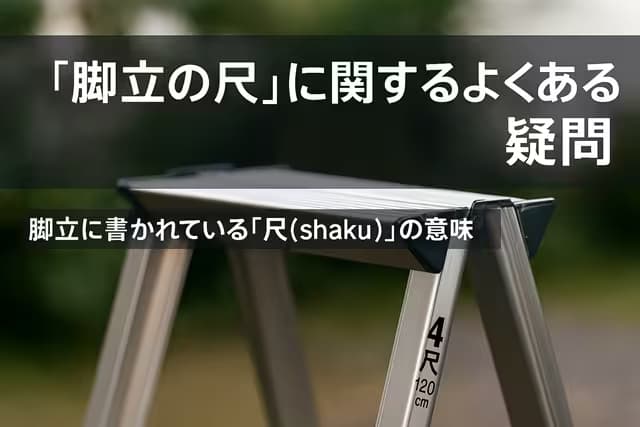
脚立に書かれている「尺(shaku)」の意味
「尺」とは、日本の伝統的な長さの単位で、1尺は約30.3cmです。
脚立における「6尺」などの表記は、その脚立の高さや到達できる作業高さを指しています。
これは、脚立の利用者が実際に登って作業できる範囲を示す指標であり、現場では非常に重要な情報です。
この「尺」は、あくまで製品の物理的寸法を示しているにすぎず、「何台あるか」を数えるための単位ではありません。
脚立を複数用意する場合は、「6尺脚立が3脚」というように、長さと数量の両方を明確に表現する必要があります。
まとめ
脚立の数え方について正しく理解することは、日常生活はもちろん、現場や業務での円滑なコミュニケーションにもつながります。
「脚」という単位は、脚立のように脚があり自立する構造のものに最も適しており、「個」や「本」ではその特徴を正確に表現できません。
また、踏み台やはしごとの違いを知ることで、より正確な表現が可能になります。
さらに、脚立に記載されている「尺」は数え方ではなくサイズの指標であり、「3尺脚立」や「6尺脚立」はあくまで大きさの違いを表しているだけです。
数える際には「○脚」という助数詞を使用することが適切です。


